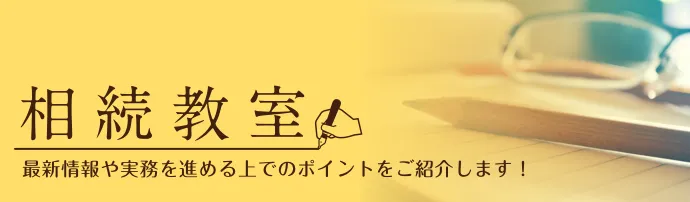
2025年06月11日
中部地方のとある旧家の男性が亡くなりました。男性の顧問弁護士が、男性が全文を手書きで書き、日付及び氏名を自書し、印鑑を押した遺言書を預かっていました。男性には三人の息子がいました。… 続きはこちら
2025年05月09日
令和7年1月8日の日本経済新聞の記事で、高齢者の身元保証に関して、トラブルが急増しているという報道がありました。その内容としては、高齢者の身元保証や死後の事務手続を家族に代わって担うサービスを巡って、消費生活センターへの相談が急増しているということです… 続きはこちら
2025年05月07日
近年では、ITの発展に伴い、色々なことがウェブ上で完結したり、電子的な対応で完結することが増えてきています。また、実際の現物よりも情報の方が価値を持つような… 続きはこちら
2025年04月16日
相続・遺産分割が争いになりますと、ある相続人は被相続人の生前に援助を受けているとか、何かもらっているという話が出て、紛争が複雑化することがあります… 続きはこちら
2025年04月10日
近年の高齢化に伴い、高齢の親などを(推定)相続人が介護する期間が長くなってきていることが考えられます。介護をする場合でも、被相続人の近隣に住んでいる親族が介護をする場合が最も多いのではないでしょうか。… 続きはこちら
2024年10月9日
身より(相続人)のない方が亡くなった場合には、最終的にその財産は国に帰属することになります。相続人がいない場合でも… 続きはこちら
2024年8月16日
令和6年6月21日に、自筆の遺言書が無効だと争われていた裁判の判決が出されました。そのような遺言書の有効性を争う裁判はある程度ありますので、… 続きはこちら
2024年7月31日
民法の改正により、特別寄与料に関する条文が新設されました。 これまでは、相続人以外で介護等を行った方は、相続人の介護と同視して関係のある相続人が寄与分を求める方法で… 続きはこちら
2024年6月20日
自筆証書遺言は、民法968条によって厳格に方式が定められ、同条の方式を満たさない遺言は無効とされます。しかし、この無効が、遺言書全体が無効なのか、要件を満たさない部分が無効なのか… 続きはこちら
2024年5月17日
公正証書遺言を遺し、父が亡くなりました。「遺言執行者として前記長男○○を指定する。」という文言がありました。私が遺言執行者に指定されたようですが、具体的に何をしたらいいので… 続きはこちら
2024年5月7日
遺言の種類として、自筆の遺言や公正証書の遺言など複数ありますが、遺言があるからといって必ずしも見つかるとは限りません。法務局が預かっていたり、公正証書遺言であれば、通常は検索することで見つかりますが、自宅に置かれていたり、第三者に預けられていたりすると、遺言書が見つからない… 続きはこちら
2024年4月12日
相続が発生した場合に、遺言等がなく、遺産分割をする必要がある場合には、相続人全員で協議する必要があります。相続人のうち1人でも欠けていると遺産分割をすることができないことが原則です。例えば、相続人の1人が高齢で認知症になっていて… 続きはこちら
2024年2月29日
遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものです。誰にどの財産を相続させるのかといった意思を表示し、意思表示どおりの効果を一方的に生じさせることが… 続きはこちら
2023年8月25日
遺留分を侵害するような多額の寄与分は認められるのでしょうか?まず「寄与分」という制度ですが、これは被相続人の財産の増加や維持に貢献したり、被相続人の財産の減少を食い止めた相続人がいた場合に… 続きはこちら
2023年8月25日
被相続人が亡くなり、相続が開始される際に、遺言書が見つかることがあります。被相続人が生前に遺言書を作成していれば、遺産をどのように分けるかは、原則としてその遺言書の内容に従うことになります… 続きはこちら
2023年8月24日
あるところに、Aさんというおばあさんがいました。Aさんは夫に先立たれましたが、BさんとCさんという二人のお子さんがいました。BさんにはDさんというお子さん(Aさんからみたら孫)がいました。Aさんは、相続税を減らすため、Dさんと養子縁組をしました。… 続きはこちら
2023年6月30日
民法上は遺産分割そのものに期限はなく、遺産分割自体が時効でできなくなるというわけでもありません。そのような場合に、遺産分割までの期間が延びるデメリットは… 続きはこちら
2023年6月23日
あるところに、Aさんという年配の男性がいました。AさんにはBさんとCさんという2人のお子さんがいました。妻に先立たれたAさんは、 Bさんに同居してもらい… 続きはこちら
2023年6月7日
令和3年に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定され、土地所有権を国に引き取ってもらう制度が新設され… 続きはこちら
2023年3月7日
相続が開始した場合、まずは遺産は、相続人間で共有状態になります。民法では898条で「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と定められて… 続きはこちら
2022年12月2日
令和3年の民法改正(2021年4月21日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、4月28日に公布されました… 続きはこちら
2022年11月24日
「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は、2023年4月1日です。その内、共有地を円滑に利用できるように、今回の改正では共有制度の見直しが… 続きはこちら
2022年09月08日
訃報は突然やってきます。ご親族が亡くなられたときには、死亡診断書の提出や葬儀場の手配、年金の受給停止手続や雇用保険受給資格者証の返還など、やらなければならない手続が当該手続がひと段落し、いざ相続人で遺産を分けるという段階になったとき、そもそも葬儀費用はどのように… 続きはこちら
2022年08月23日
「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は2023(令和5)年4月1日です。改正された内容の一つとして、隣りの土地について、相互の所有者が、自分の所有地を利用しやすいよう調整し合う関係(相隣関係)の規定について改正が… 続きはこちら
2022年07月18日
「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は2023(令和5)年4月1日です。改正された内容の一つとして、隣りの土地について、相互の所有者が、自分の所有地を利用しやすいよう調整し合う関係(相隣関係)の規定について改正が… 続きはこちら
2021年06月24日
遺産を遺すために生前から準備をする際に、遺産をどのように分けるか、誰に何を遺し、相続させるか、という観点から遺言等を準備することがあります。逆に、(推定)相続人のうち、誰かには相続させたくないという気持ちで遺言等を準備することも… 続きはこちら
2021年05月27日
相続人に遺言の内容の実現が困難な場合や相続人が複数いる場合に、効率よく遺言を執行できるのが遺言執行者の制度ですが、遺言執行者の報酬はどのように決まるのでしょうか。 続きはこちら
2021年04月28日
死亡保険金は、残された家族の生活保障という目的を持つ遺産のため、一定の範囲内(500万円×法定相続人数)であれば、非課税とされています。 続きはこちら
2021年12月08日
相続が発生した時には、いったん共有で登記をしたり、遺産分割が成立すればその内容に従って登記をしたりしていました。 続きはこちら
2021年11月10日
相続の際に、遺産の中に賃貸物件(収益物件)が含まれていることがあります。近時では、ワンルームマンションの1部屋単位の投資もありますので、こういった賃貸物件(収益物件)が遺産に含まれることも増えてくるかもしれません。… 続きはこちら
2021年6月23日
2021年1月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、贈与契約に基づく預金の支払請求が、「公序良俗に反して無効」と判断される判決が出された… 続きはこちら
2021年5月12日
改正前民法1016条では、遺言執行者は、・やむを得ない事由あるもしくは・遺言者が第三者に任を担わせてもよいと遺言書に記載していたという事情がなければ… 続きはこちら
2021年3月17日
2021年2月10日、法制審議会が、土地の相続や登記、管理に関して現行の制度を大きく変更する法改正に向けた答申を出した。という報道が… 続きはこちら
2020年7月8日
令和元年8月27日、最高裁判所で、相続の開始後に認知によって相続人となった人が遺産の分割を求める場合の、請求金額の計算方法に関する判決が出されました。この判決の内容を見る前に… 続きはこちら
2020年4月22日
配偶者が亡くなった場合、葬儀費用や当座の生活費用など何かと費用がかかります。しかし、亡くなった配偶者名義の預貯金口座からお金の払戻しを受けたくても、原則銀行は相続人全員の同意がなければ… 続きはこちら
2020年4月22日
高齢化の進展とともに、認知症になる高齢者も増えてきているかと思われます。この場合、年金が預金口座に入金されても、どのように引出しをするのかという問題が発生することも… 続きはこちら
2020年3月12日
相続人以外の親族(特別寄与者。例えば相続人である長男の嫁)が無償で被相続人の療養看護などをしていた場合、その者は相続人に寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できることになりました… 続きはこちら
2020年1月11日
2019年12月27日の日本経済新聞の記事で、同新聞社が直近の国政調査を分析した結果として、郊外の宅地開発が止まらないことにより、2015年までの10年間で、大阪府に匹敵する面積の居住地区が生まれたことが…続きはこちら
2019年12月12日
裁判所のホームページに載っている成年後見関係事件の概況(平成30年1月から12月)によれば、平成30年の後見開始、保佐開始、補助開始、および任意後見監督人選任事件の申立件数は、3万6549件となっているようです。…続きはこちら
2019年11月06日
民法の相続関係の分野の改正により、 配偶者居住権の制度が設けられることになりました。配偶者居住権に関する規定は、2020年4月1日から施行されることになりますので、 現時点ではまだ明示的に配偶者居住権の規定を用いることはできませんが…続きはこちら
2019年11月06日
高齢化や少子化の進展、権利意識の高まりに伴い、成年後見人が選任される場合が増えてきています。しかし、成年後見人の業務は、原則として被後見人が亡くなってしまうと終了しますので、亡くなった時点で、亡くなった後の事務をどのようにするのか問題がありました。… 続きはこちら
2019年10月17日
2019年9月21日の日本経済新聞に、遺留分の規定が、改正された相続関連法規によって思わぬ課税が生じる可能性があり、注意を促す記事が掲載されていました… 続きはこちら
2019年7月26日
遺言書がない場合、民法の法定相続分で相続するか、法定相続分でなければ遺産分割協議で遺産を分割して相続することになります。その遺産分割協議に期限はあるのでしょうか?… 続きはこちら
2019年7月5日
被相続人が亡くなり、遺産分割をする際に、葬儀費用の負担が問題になることがありますが、葬儀を誰が執り行うかが問題になることもあります… 続きはこちら
2019年4月11日
自分の葬儀を生前に取り決めておき、相続人の負担を減らしておこう。遺産分割に加え、いわゆる「終活」の一環として、葬儀の方法を遺言に盛り込みたいと相談を受けることがあります。実は、葬儀の方法は、… 続きはこちら
2019年3月26日
遺言といっても、民法では色々と定められています。民法960条には、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」とされています。そのため、民法に定めた方式に従わなければ、せっかく遺言書を作っても、効力がないとされる可能性があります… 続きはこちら
2019年1月25日
遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、遺贈や生前贈与などにより特定の者にだけ財産が遺された場合にも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に限って、一定割合の遺産の取り分(遺留分)を請求できる制度です … 続きはこちら
2019年1月17日
被相続人名義の不動産を、遺産分割をしないまま、相続人の一人が占有し続けているという場合、遺産分割をするまでもなく、取得時効により当該不動産の所有権を … 続きはこちら
2018年9月12日
平成30年7月6日、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立し、同月13日に公布されました。このうち、遺産分割に関する見直しについてお話します。 … 続きはこちら
2018年9月6日
平成30年7月6日、民法や家事事件法などの一部が改正されました。前々から議論されていた配偶者居住権などが新設されることになりましたが 続きはこちら
2018年8月27日
生前から遺産分割の準備をしておく方法として代表的なものは、遺言書の作成、生前贈与をする、死因贈与契約、といったものが代表的なものだと思います。ただ、どれも一長一短の特徴があります。例えば.. 続きはこちら
2018年8月6日
日本経済新聞に、2018年度の税制改正で一般社団法人に対する課税が強化されるという記事がありました。 記事では、これまでは一般社団法人に関する相続税は事実上課税されなかったということです… 続きはこちら
2018年5月29日
最近の報道によれば、現在、法制審議会の民法部会で、相続分野に関する民法の改正を検討しているようです。 具体的にどのような変更を検討しているかと言えば、 … 続きはこちら
2018年4月9日
相続、遺産分割の際に、長期間にわたって登記の変更がされていない不動産が見つかることがあります。普段は使われていない土地・建物や、先祖から引き継いだ山林・田畑など、相続人が普段接しない不動産や、遠方にある不動産は、相続が開始されても、 … 続きはこちら
2018年2月27日
最近では、世界でのキャッシュレス化が報道されています。募金を現金ではなく電子的に支払ったり、現金での支払いを断る店舗も出てきているという話もあります。日本は、世界の他の国と比較して、現金での支払いや取引が多いと言われています … 続きはこちら
2018年1月17日
少子化や未婚化・非婚化の流れとともに、今後、子供や兄弟のいない方が亡くなり、そこから問題が発生することも予測されます。子供や兄弟といった相続人がいない場合には、その人の残した負債をどうするかといった問題があります。例えば、 … 続きはこちら
2018年1月5日
遺言がない場合には、亡くなられた方の遺産について、原則、相続人で遺産をどう分けるのかを決める遺産分割協議をする必要があります。協議の内容は、通常、「遺産分割協議書」という書面にまとめられます … 続きはこちら
2018年12月29日
遺産分割の協議や調停をする場合には、相続人全員が関わる必要があります。相続人全員の関与がなければ、 … 続きはこちら
2017年12月11日
遺産分割をする際に、相続人のうち1人でも重い認知症にかかっていて、どのように遺産分割できるか判断できない人がいた場合、その人には後見人を … 続きはこちら
2017年3月30日
相続では、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産、つまり借金・負債も相続することになります。民法では、896条で、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」とされています… 続きはこちら
2017年5月11日
相続の問題として、相続人がいない場合というのが考えられます。相続人がいないことによる問題は、負債はなく財産がある場合、財産はなく負債がある場合、財産も負債もある場合の3つに分けられます。… 続きはこちら
2017年5月18日
遺言書で、ある財産を全て1人の相続人に相続させる旨の遺言書が見つかることがあります。そのような遺言では、負債について何も取り決められていない場合も見受けられます… 続きはこちら
2013年8月12日
相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が、生前に被相続人から不動産やお金などの「贈与」を受けたり、遺言書で他の相続人に先んじて遺産を受け取ることを指定(遺贈もしくは分割方法の指定)されたりする場合があります… 続きはこちら
2017年01月27日
前回は、民法904条で、「受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったとき」のことについて考えました。 … 続きはこちら
2016年9月07日
人が亡くなった場合、相続人がいれば、相続人の協議により亡くなった人の財産をどうするか決めることになります。 しかし、もともと相続人がいない場合もあり得ます。 … 続きはこちら
2015年9月25日
遺産分割協議をするにあたり、被相続人が事故などで若くして亡くなってしまいますと、相続人の中に未成年の子どもがいる場合も少なくありません。… 続きはこちら
2015年8月10日
相続が発生した際には、まずは被相続人の遺産がどの程度あるかを調べる必要があります。また、遺産分割の際には、特別受益が問題になることがあります。… 続きはこちら
2015年1月16日
最近では、一般の方々の間にも相続に関する法律の知識が広まっており、日常の業務の中でも、相続人間で法定相続分(各相続人が取得する遺産の割合)に争いがあるというお話はほとんど聞かなくなりました。 しかし… 続きはこちら
2015年1月16日
被相続人が亡くなられて、遺言書が作成されていなかった場合、相続人は全員で協議して遺産分割をしなければなりません。そして、この協議をまとめ、書面化しなければ、法務局は不動産の名義変更に応じてくれませんし、… 続きはこちら
2014年11月7日
昨今、改正相続税法が、平成27年1月1日から施行されることに伴い、一般の方々向けの雑誌でも「大増税」等の文字が躍り、世間では相続対策の必要性・重要性が見直されています。 増税というのはあまり喜ばしいことではありませんが… 続きはこちら
2014年7月30日
平成26年7月17日、最高裁判所で、親子関係とDNA鑑定に関する判決が出されました。概要としましては、嫡出否認の手続が取れない場合で、DNA鑑定によって親子関係がないことが明らかになったとき、法律上の親子関係を否定することができるか、といったものでした… 続きはこちら
2014年6月19日
前回、遺産における使途不明金を巡ってどのような問題があるかを説明しました。では、具体的に、遺産における使途不明金をどうやって解決させればいいのでしょうか。まず、使途不明金は、遺産分割協議や遺産分割調停で解決できる場合と解決できない場合があります。使途不明金は、生前に預金などから引き出されたお金であれば… 続きはこちら
2014年6月13日
相続が発生する前も後も、「使途不明金」が問題になることがありますこで言う「使途不明金」とは、被相続人が亡くなる前や後に、被相続人の現金が持ち出されたり、被相続人名義の預金口座から預金が引き出されているけれども、その使い道が分からないといったお金のことを指します。被相続人が亡くなった後の場合… 続きはこちら
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会