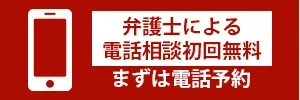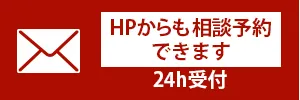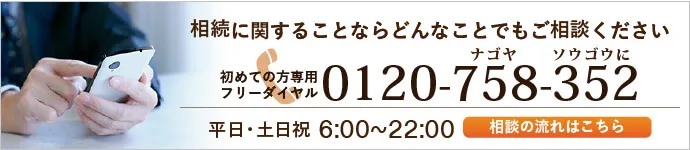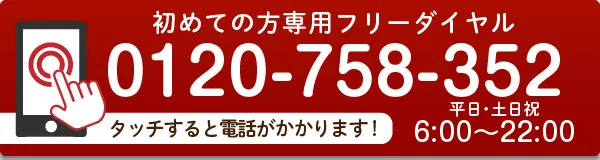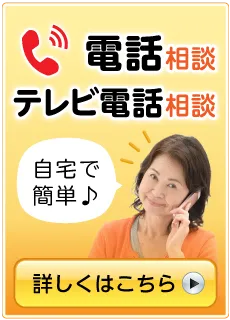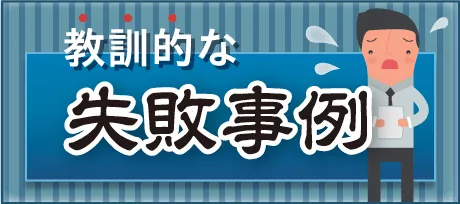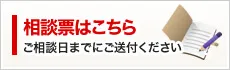農地法が平成21年12月15日に改正されたことに伴い、改正後に農地を相続等で取得した場合、農地の所在地を管轄する農業委員会へ届出
が必要になりました(農地法第3条の3第1項)。
届出が必要となるのは、相続等(法定相続分での相続のほか、遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈、遺留分減殺による取得を含みます)により農地を取得した方です。
届出の期間は、農地の権利を取得したことを知った時からおおむね10ヶ月以内です。
相続により、農地の権利取得の効果は既に発生していますので、届出は事後的なものとなります。また、届出とは別に、権利取得を公示するためには、法務局への登記手続きが必要となります。
なお、相続人以外の第三者への特定遺贈や、死因贈与による場合には、事前に農地法の許可を得なければ、所有権を移転することができません。所有権移転登記手続きには、添付書類として農地法の許可書が必要です。
農地を相続で取得した場合に農地法の許可が不要なのは、相続人が農地をそのまま農地として相続する場合です。
その後、相続後に権利の移転や、転用(農地から宅地へ)を行う場合には農地法の許可が必要となります。農地を相続し、そこに家を建てようとする場合や、農地を相続したが耕作することができないので売却する、などの場合はやはり許可が必要となるのです。
農地を相続したけれど地元を離れていて自分では農地の手入れができない場合など、農地の管理について農業委員会に相談すると、地元で借り手を探す手助けをしてもらうこともできます。届出の際に、農業委員会によるあっせん等の希望の有無を記入することができます。詳しくは、農地の所在地を管轄する農業委員会にお問い合わせください。
農地を農業目的で使用している限りにおいては到底実現しない高い評価額によって相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じるため、自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために、昭和50年度に創設されました。
従来、相続税の納税猶予制度は、相続人自らが農業の用に供する場合のみを対象としていましたが、農地の効率的な利用を促進する観点から平成21年度に改正され、市街化区域外の農地に限り、特定貸付け(※)を行った場合についても適用できることとなりました。
※特定貸付けとは…①農地中間管理事業、 ②農地利用集積円滑化事業、 ③利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)により貸し付けることをいいます。
相続又は遺贈により取得された農地が、引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除されます。
※農業投資価格とは…農地等が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立すると認められる価格として国税局長が決定した価格 (20万円~90万円程度/10a)をいいます。
事務所外観

名古屋丸の内事務所

金山駅前事務所

一宮駅前事務所

岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会